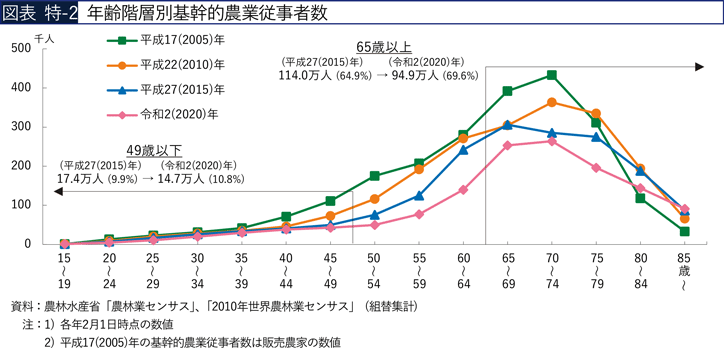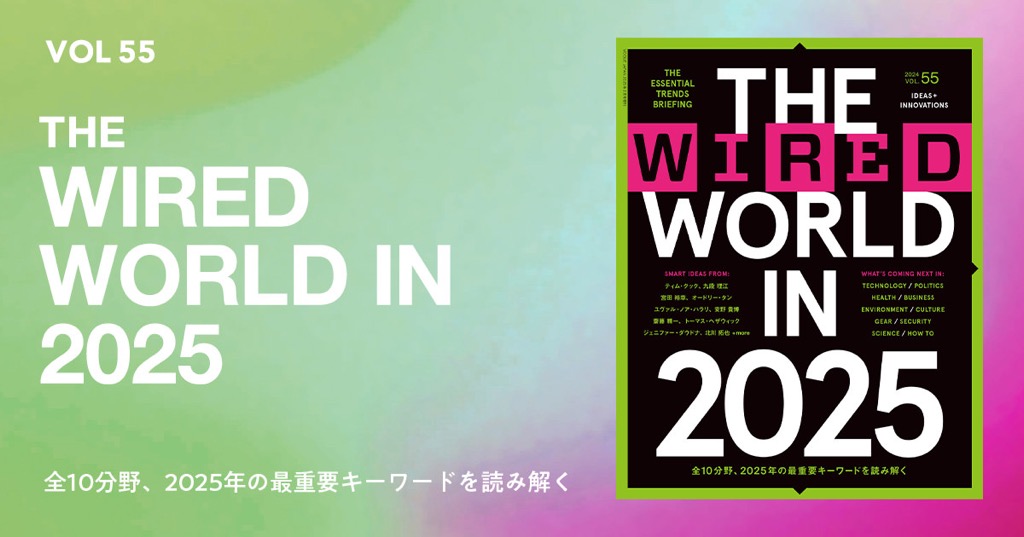農事組合法人の設立についての相談がありました。同時に法人として、農地を転用して作業場を建てたいということで、農地転用の申請の依頼もいただきました。うちと同様に、稲作なので、事業計画もラクでしょう。今年の米価は異常なので、大臣も代わり、来年は元に戻ることを想定するとして、どうして、水稲農家は儲からないのでしょうか。儲かる農家、と言われて久しいわけですが、ほとんどの農家は儲からない。
なぜ儲からないのか
農業も事業なので、事業計画があるはずです。収入を見込み、経費を計算し、利益を算出するのは、農家も行政書士も同じです。これを複数年分のシュミレーションして、月次の資金繰りをたて、事業計画を作成するわけです。農業委員会には5年分の事業計画書を提出しますが、10年以上の長期の計画が必要です。特に稲作は年に1回しか収穫できないので、毎年の積み重ねが重要です。今月、営業が足りなかったから、来月は頑張ろうとはいかないんです。
損益分岐点、というのがあります。事業計画ではとても重要な指標です。期待される収入と、投入する経費、特に稲作の場合は機械が高額なため、固定費が大きな割合を占めます。
稲作の収入は作付け面積でほぼ決まります。米価はJAや商系であっても大きく差はありません。よほど特別な栽培で、売り先があれば別でしょうが、ほとんどの農家はその地域の米価がベースとなります。となると、その収入は作付け面積によって決まっているというわけです。田んぼの10aからの収量は、地域差こそあれ、ほとんど決まっています。そうなると、作付け面積によって、損益分岐点が決まってくるのです。個人的な感覚でいうと、5haが損益分岐点かも、というところでしょうか。当然、その利益でもって生活していくわけですがから、その分を加味すれば、10haは必要です。ところが、地元の平均耕作面積は2.5ha程度です。儲かるわけがないのです。
農業は家業
儲かるわけのない、農業をなぜ続けるのか、それは家業だからです。先祖から引き継いだ農地を守る、というのが農家のミッションです。だから、続ける、続けられる。
日本において全国民に米が行き渡ったのは戦後です。米が価値があった時代は、それを生み出す農地は資産でした。なので、農地があることが富の象徴であったわけです。ところが、米が余りだしてからは、それは負債であり、近年は農地にはほぼ資産価値はないとされてきました。
二つの構造
農家が儲からないのはこうした時代の背景がありました。農家が儲かるためには二つのボトルネックがあると思います。
一つは農地自体が収入の糧であったため、農地に対する農家の執着が強い。日本の農業で問題とされるのは、生産性の低さですが、小さく耕作効率の悪い農地であったとしても、生産効率を考えず、その土地を維持、というよりは守ろうとする、というマインドが働いてしまうのです。事業として効率を考えれば、効率を優先して、交換するなりして集約できるはずなのに、なぜかそれができないのです。一方で、近年は農地離れが進んでいる傾向にあるとも感じます。離農する農家が増えて、農地に固執しなくなりつつあるのかもしれません。
もう一つは、専業の壁です。稲作農家のそのほとんどが、兼業農家であり、それも農業以外を主たる収入とするものです。先ほどらいの儲からない農家のほとんどは、主たる収入からそれを補填するかたちで、農業を維持してきました。フルタイムで働きつつ、農業をするのは、おそらく3haくらいが限界であろうと思います。休日をフルに使い、しかも農作業は天気にも左右されるため、それでも足りないくらいだと思います。そうなると、現在の耕作面積を維持しようというマインドが働きます。先ほど説明したとおり、この経営規模だと、経営がままならない、だから主たる収入で補填する、この悪循環が専業農家への壁となっているのです。
もう一度損益分岐点を考える
60歳が定年退職である時代は過ぎましたが、退職してから農業を、という人は少なくありません。退職後に専業農家としてやっていく、という人はある程度いる一方で、事業化できる人は一握りだと感じています。結局、個人一人でできる規模というのは決まってしまうので、それボトルネックになってしまっているのです。事業計画をちゃんとできると、人を雇って、できることが広げることができるはずなんです。それができなくて、いつも事業主だけが大変な思いをしている農家はたくさんいます。
しかも、スマート農業の時代、新しいテクノロジーが次々と採用されている昨今、その最新技術にもアクセスできていないという現状もあります。
この辺の感覚があると、自分があとどれくらい「ラク」ができるかが見える化できるのですが、従来のどんぶり勘定でやっていると、ちょっと無理かな、ってなりますね。
家業から事業へ
「農家」という言葉がなくなればいいと思っています。残るのは農業経営者であり、農業を事業化できるマインドを変えていかなくては、これからの農業を続けることは難しいです。
今年は、米価がバグって、弊社もおかげさでありましたが、宝くじにあたったみたいなものなので、来年以降も気を引き締めていきたいと思います。